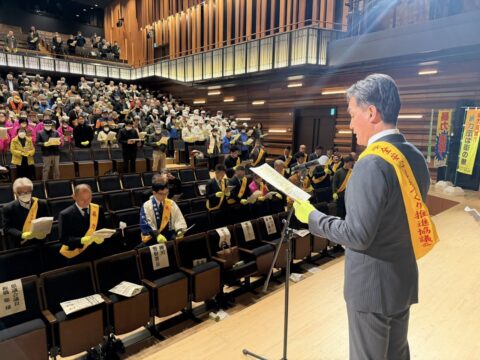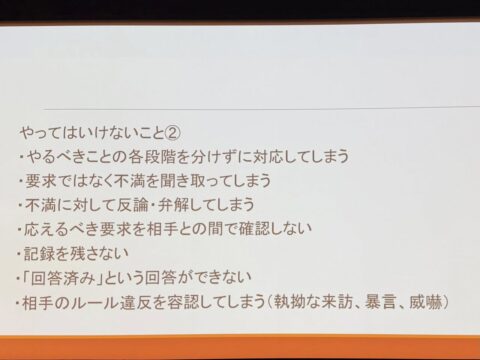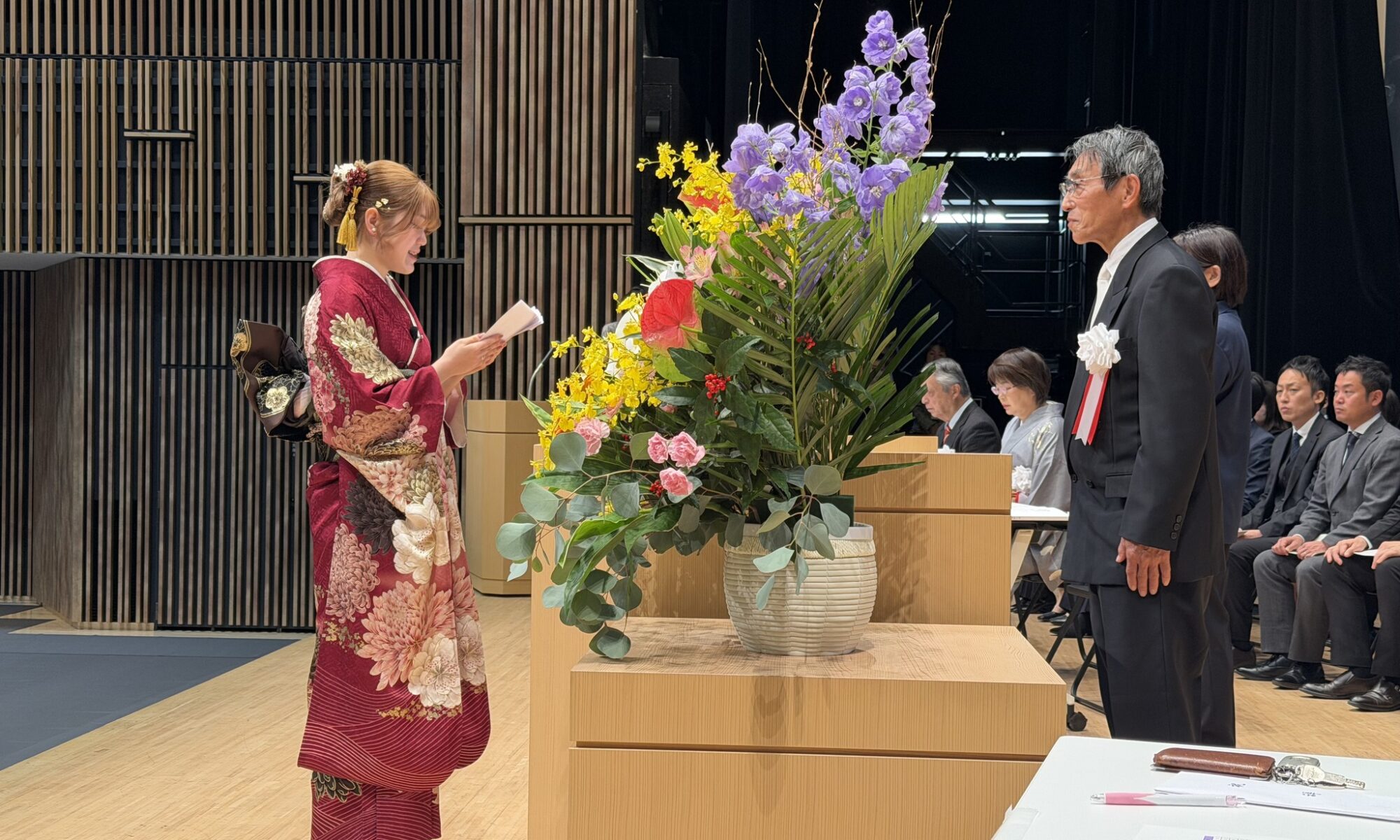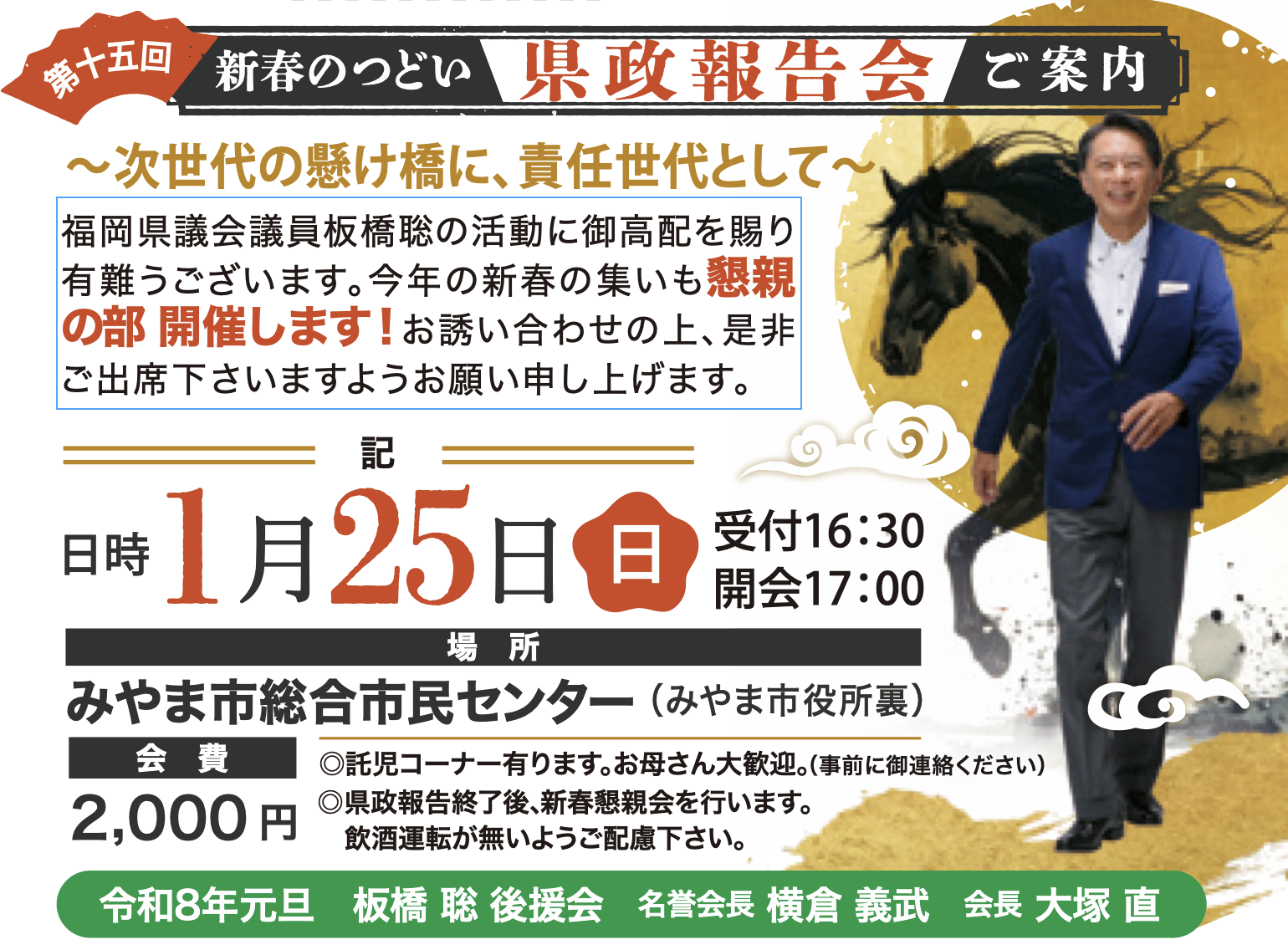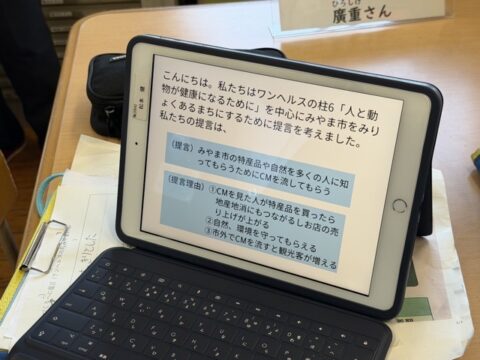私が所属する総務企画地域振興委員会が7年11月17日から19日にかけ管外視察を行いました。備忘録代わりに書き留めておきます。
◎ 石垣市役所新庁舎:離島の切実な危機管理と特定避難施設
最初に訪問した石垣市役所新庁舎は、令和3年11月15日に供用開始された新しい庁舎です。

石垣市の直面する最大の課題は、武力攻撃を想定した特定臨時避難施設(シェルター)の整備です。石垣島は沖縄本島から410km、お隣の台湾からはわずか280kmと近接しており、広域避難の困難性がある地域と見なされています。国は、武力攻撃よりも十分に先立って住民の広域避難を完了することが最も重要としつつも、避難が困難な地域では一定期間(2週間程度)避難可能で堅牢な特定臨時避難施設の整備が必要である、との考え方を示しています。

石垣市では、市役所隣接地に整備予定の防災公園の地下を、平時は駐車場として利用し、有事の際に特定臨時避難施設として活用する計画を進めています。収容人数は500名を想定し、1人あたり2㎡として概ね1,000平米の施設規模が計画されています。構造体は、外部に面する壁などが厚さ30cm以上の鉄筋コンクリート造が基本です。

この計画に対し、委員からは、有事の際に民間航空機が飛ぶ保証があるのかという広域避難の実行性への疑問が率直に提起されました。広域避難が不可能に近いのならば、500人規模ではなく、より多くの市民を守るための大規模な地下施設(シェルター)を国が責任を持って整備すべきではないか、という切実な意見も出されました。この議論は、離島地域特有の、危機管理の根幹に関わる重く困難な課題を浮き彫りにしました。
◎ チャレンジ石垣島:地域課題を乗り越える若者の自立
民設民営の「チャレンジ石垣島」を訪問しました。この施設は、イベントスペースとコワーキングスペースを併設した地域の発信拠点です。

特筆すべきは、高校生を対象とした市の委託事業である「石垣市公営塾」です。この塾は学力向上を目的とせず、「自分と向き合う場所」をコンセプトに、キャリア教育や探究学習を提供しています。生徒たちは、島内の課題をテーマにプロジェクトを立ち上げ、単なるレポートで終わらず、といった「形にする」実践的な活動を行っています。講師は、答えを与えるのではなく、「どうしたらいいと思う?」と問いを返す伴走者としての対話重視の指導を徹底しており、この活動が総合型選抜(旧AO入試)での大学進学に直結している事例が多く見受けられました。

◎ 那覇第2地方合同庁舎3号館:災害時の命綱、簡易設備の革新
那覇新都心地区に整備された那覇第2地方合同庁舎3号館は、災害応急対策に従事する4つの国官署が集約された防災拠点庁舎です。ここでは、停電時に最大1週間(168時間)連続稼働できる大容量の自家発電設備を備えるなど、強固な災害対策が施されています。
特に注目したのは、災害発生時に帰宅困難者や職員の生活を支える「かまどベンチ」と「マンホールトイレ」といった簡易ながら実用性の高い設備です。

かまどベンチは庁舎前の前庭に設置されており、普段はバス停のベンチとして使われています。災害時には、座面を外して炊き出し用のかまどとして使用し、温かい食事を提供できます。デモンストレーションでは、ベンチが容易にかまどへと変形する様子が確認でき、災害時の食料確保の重要性を再認識しました。

庁舎の敷地内には、緊急時に利用できるマンホールトイレが5箇所設置されています。地震などで下水管が断絶し、通常のトイレが使えなくなった場合、下水道の経路を切り替え、マンホールの下にある貯蔵層に排水を貯める仕組みです。デモンストレーションでは、マンホールの上に便座と簡易テントが設置される様子が示され、この便座にはロック機構があり、内側から施錠することでマンホールが動かないようになっているなど、実用性への工夫が確認できました。合計5つのホールがあるため、男性用、女性用、車椅子用などに分けて利用可能であり、その簡易性と機能性は、災害時の衛生環境維持にとって極めて重要な対策だと感じました。

◎ まとめ
今回の沖縄視察は、特に危機管理と防災の分野において、離島地域と本土側の最前線の取り組みを深く比較検討する機会となりました。
石垣島における特定臨時避難施設の議論は、広域避難の困難性という地理的制約と、それに対処するための堅牢なシェルターの規模に関する本質的な課題を提起しました。これは、単なる地方行政の枠を超え、国の安全保障政策における責任と財政措置のあり方について、私たち総務企画地域振興委員会が今後も深く検討すべきテーマです。
一方、那覇で確認したかまどベンチやマンホールトイレは、災害発生時の「生きるための環境」を確保する上で、いかに日常的なインフラの整備と、簡易的な設備の備蓄が重要かを明確に示しました。これらの視察結果は、福岡県の防災・危機管理体制の強化、そして地域振興の企画を進める上での具体的な教訓となりました。
今回の視察を今後の県政運営に反映させるべく努力して参ります。
https://youtube.com/shorts/WHF8y8UhsBo?feature=share