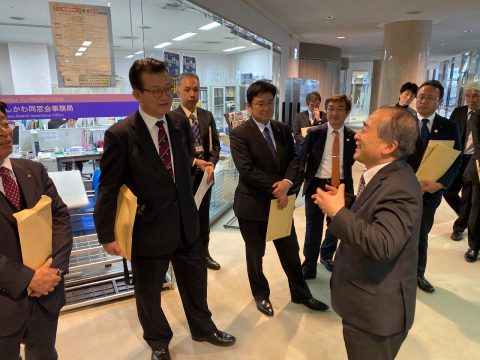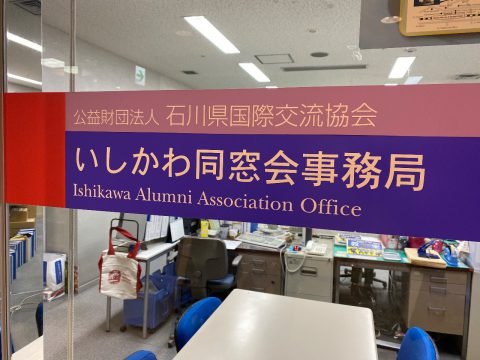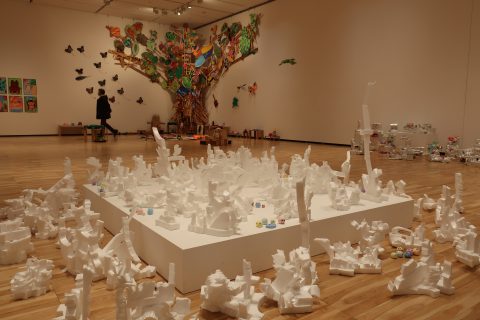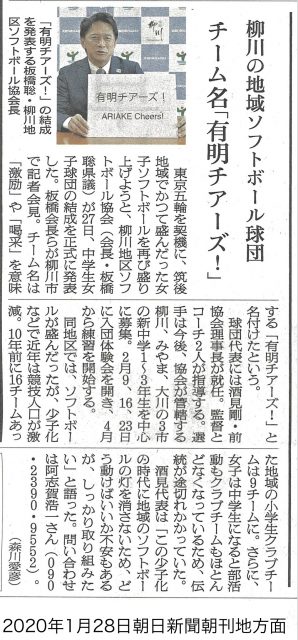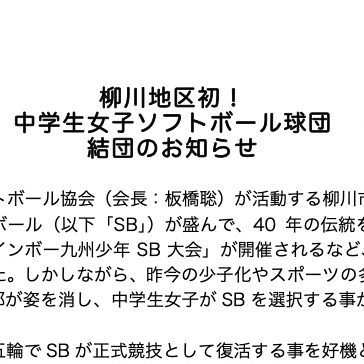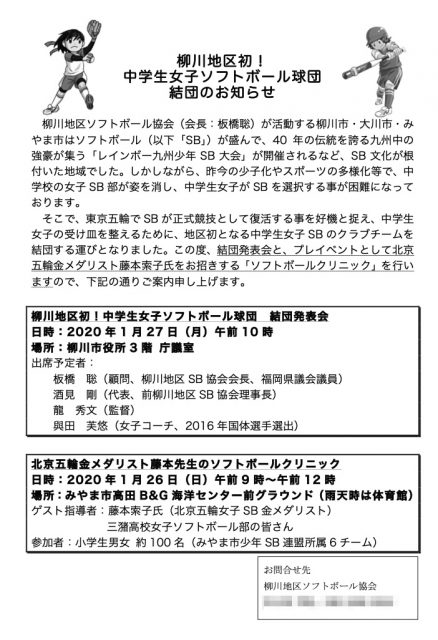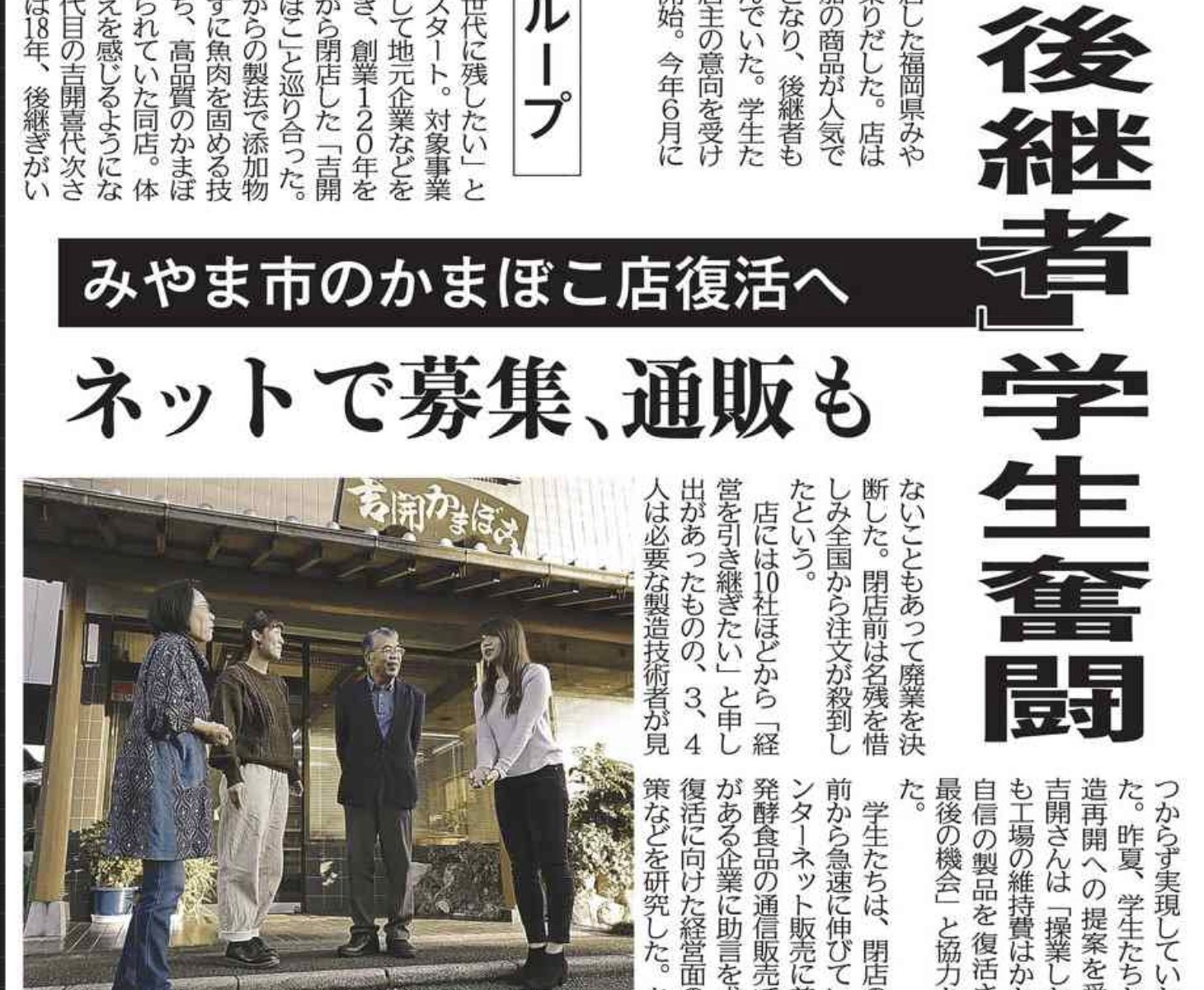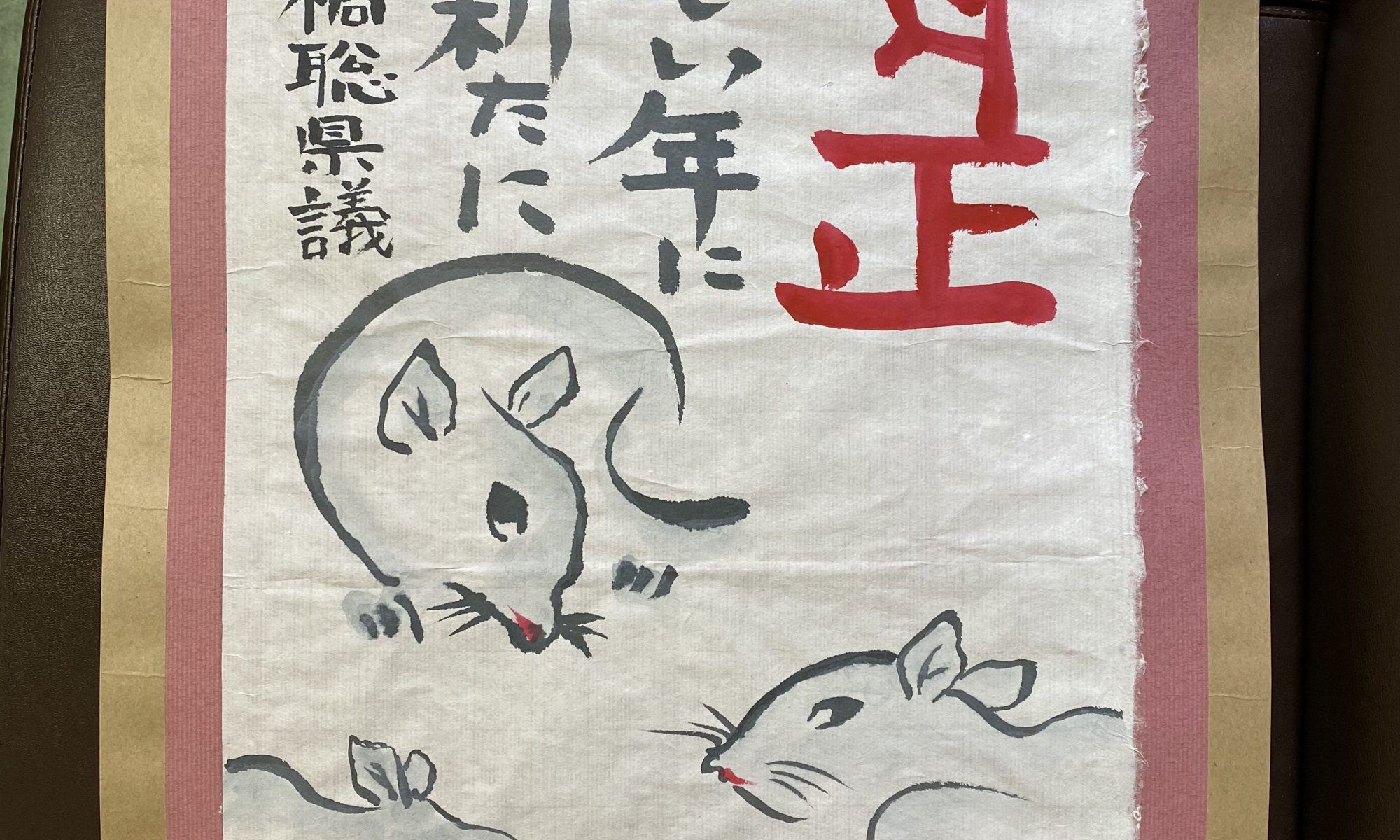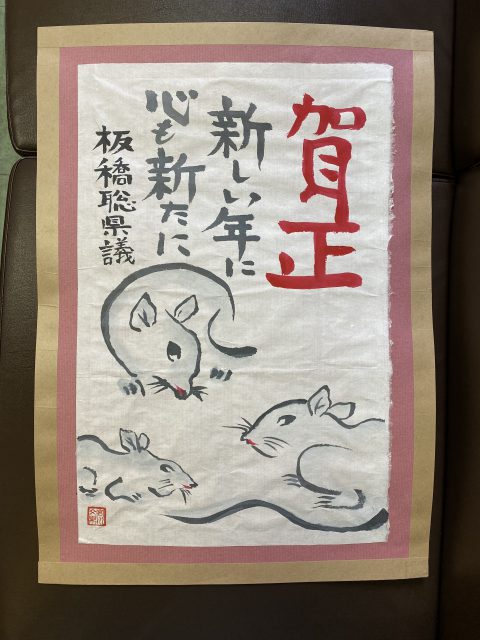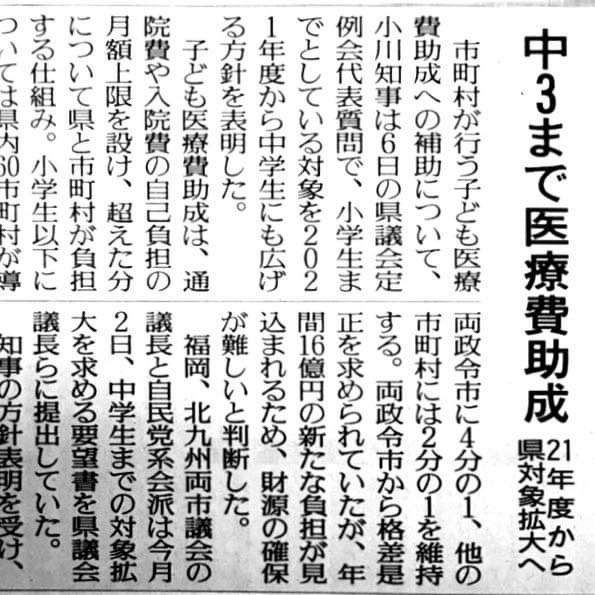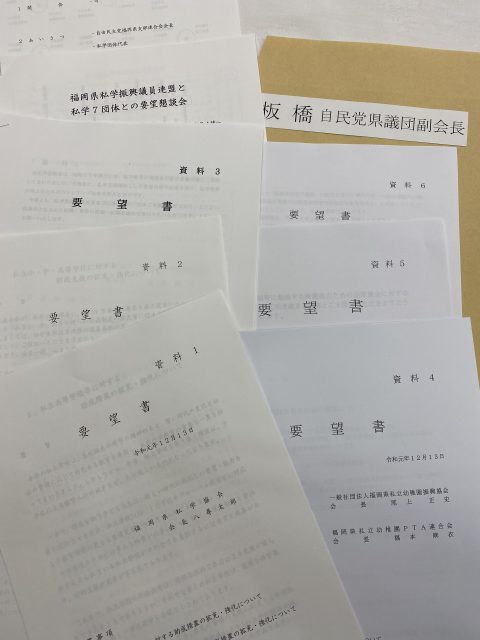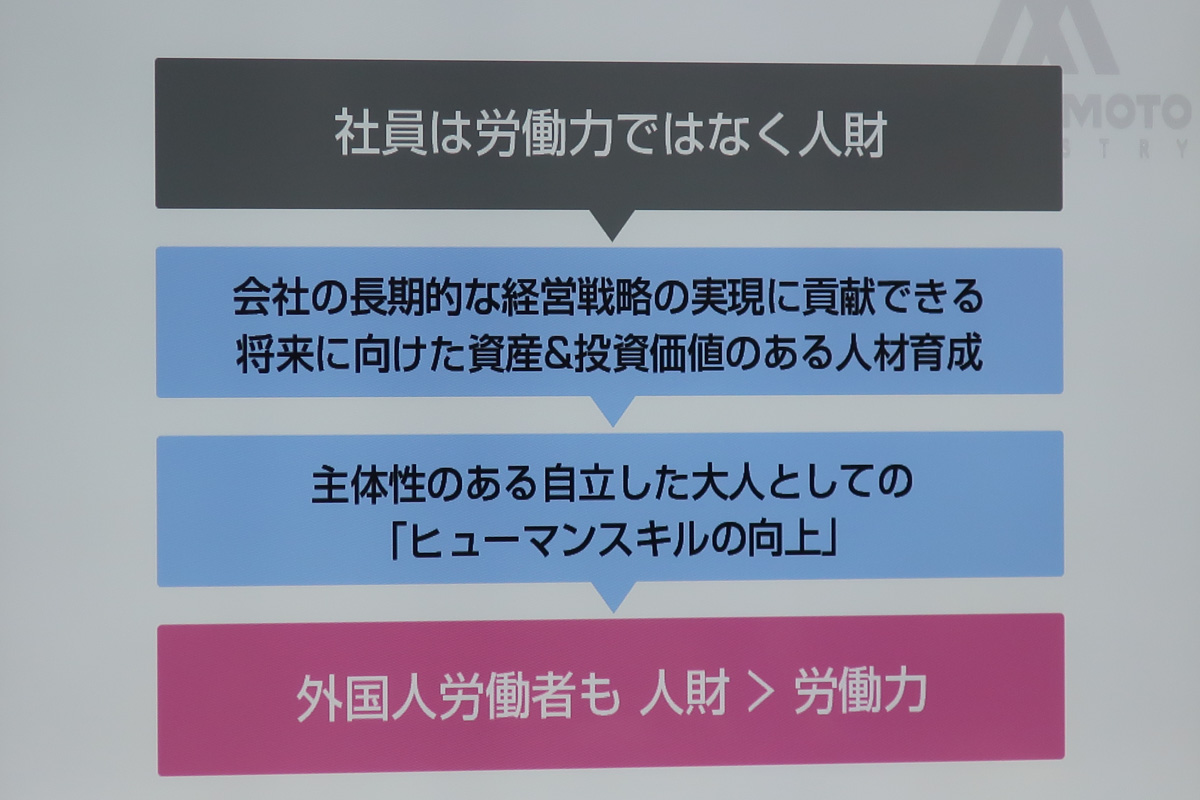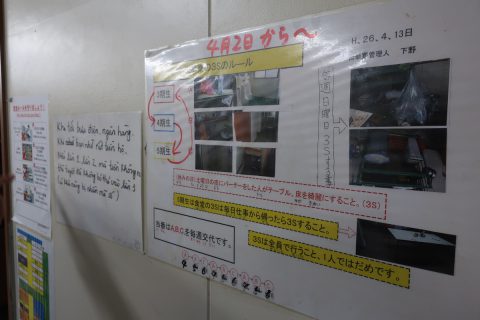私が所属する総務企画地域振興常任委員会で2月3ー4日に管内視察が行われました。備忘録代わりに書きとめておきます。
◯ 県庁 災害対策本部及び防災関連システムの整備
以前は県庁9階に設置されていた災害対策本部室ですが、(1)通信速度が遅く大容量化やデジタル映像に対応できない、(2)主流のIP方式に対応していなかった、(3)無線設備の多くが特注品で、整備費・維持費が高価、(4)大規模災害に対応できるスペースが不十分、などの理由から再構築され、平成31年4月に県庁3階に新災害対策本部室が完成。また同時に運用が開始された防災情報システムを視察しました。

平成24年の北部九州豪雨災害の時は自衛隊・消防本部などからの応援部隊が入りきれない程手狭だったのですが、面積が従前の337平米から666平米と約2倍の広さになり、十分余裕を持って対応が可能となりました。

また、高速大容量の光回線を活用する事で、大量の情報を高速配信出来るようになり、同時にIP化する事で、設備の相互接続・調達が可能となりコスト削減も実現しております。
新たに導入されたLアラート(災害情報共有システム)では各市町村の被害情報などを様々なメディアを使って共有するシステムです。が、これ現場の市町村が被害情報を適切に入力しなければ絵に描いた餅となります。
Lアラートに実効性を持たせるために、毎年防災情報システムの研修を市町村向けに行い、各地域で適切な運用が出来るようにしています。

また、「SPECTEE」というサービスを導入していましたが、これが結構すごいシステムでした。Twitter、Facebook、YoutubeなどのSNSをAIで分析し、福岡県内の災害について呟きがあった場合、即時に状況をサマリーし、画像付きで報告してくれます。実際我々が視察している間にも、県内某所で水道管が破裂したとの速報が飛び込んできました(ソースは一般人のTwitter)。身近に災害が発生した場合は、一般の方でもTwitterなどで画像とジオタグ付きで呟けば、先ずは第一報が県の災害対策本部に通知されますので、是非積極的に呟いて欲しいなぁと思います。
実は私、2012年10月の決算委員会で、災害発生時に現場にいる消防団の方々がスマホで位置情報付きの写真を写して、それをアップロードしてマッピングするようなシステムを作れば即時状況把握に効果があるのではないか?と質問をしました。
平成23年度決算特別委員会質問「自主防災組織の育成と災害時の情報収集」
https://itahashi.info/blog/20121030091558
当時、執行部から前向きな回答は頂きましたが、インフラ的に対応が出来ずきちんと実現できていませんでした。こういう形であの時思い描いた近未来が実現しているとは!AIと集合知の融合ってやつなんでしょうか。未来がやってきたなぁと感激した次第です。
◯ 福岡県職員研修所の概要
県職員研修所は、昭和26年に福岡市百道で新築落成、その後昭和63年2月に大野城市に「福岡自治研修センター」として新築移転し今に至ります。

「福岡自治研修センター」は県職員研修所・市町村職員研修所が共同で管理運営。敷地面積34,644平米、研修室、体育館、食堂、宿泊施設を備えています。宿泊棟には県146人、市町村118人が収容可能です。

平成14年より研修業務をアウトソーシングして、以前は23人いた職員を6人に減らし、約132百万円/年の経費削減効果がありました。

昨今は職員数の減少に伴い、研修受講者はピーク時に比べて減少。土日祝日や宿泊研修の無い平日は宿泊棟が稼働しておらず、施設を更なる利活用する余地があります。
また、施設設備が新築から30年以上経過し、老朽化が目立ち、女性職員の増加、障害者・性的少数者への配慮にも対応できていません。

そこで、老朽化した施設の改修に合わせ、スポーツ合宿や企業等研修を受け入れを可能とし、将来的な施設の有効活用を目指します。令和2年から設計改修をおこない、令和5年以降一般利用開始する予定です。

この研修所の隣は大野城市の市営グラウンドで、研修所自体が体育館を持っていることから、天候に左右されないスポーツ合宿施設として大きな可能性があるのではと思います。我がみやま市も廃校となり使われなくなった(あるいは今後、使われなくなる)小学校の活用で苦慮しているようですが、こういった事例を参考に、積極的で前向きな策を講じて欲しいと期待します。
◯ 北九州東県税事務所 県税の状況について
北九州東県税事務所は、収税業務として門司区・小倉北区・小倉南区、課税業務としてそれに加えて京築地区2市5町、地方税収対策本部として北九州市全域と遠賀地区1市4町、京築地区2市5町を管轄区域とします。

65名の職員のうち男女比率が6:4で県庁平均と比較しても女性の比率が高く。班長以上の役職者比率は男女比率4:5で女性登用が進んでいます。また専門性が必要とされるため、10年以上の税務経験年数を有した方々が55%超いらっしゃいます。
税の公平性を保つため、逃げ得は許さない信念のもと、毅然とした対応で県税の賦課徴収を行われています。また、徴税の際に謂れのない罵詈雑言を受けることがあったり、一方で、県民の方々に寄り添う気持ちを忘れず、生活状況などを考慮して適切なアドバイスを与えるなど、実際の業務上では大変ご苦労もあるとの事でした。
以上、駆け足でレポートです。今後の県政振興の為に今回の視察内容を有効活用していきたいと存じます。