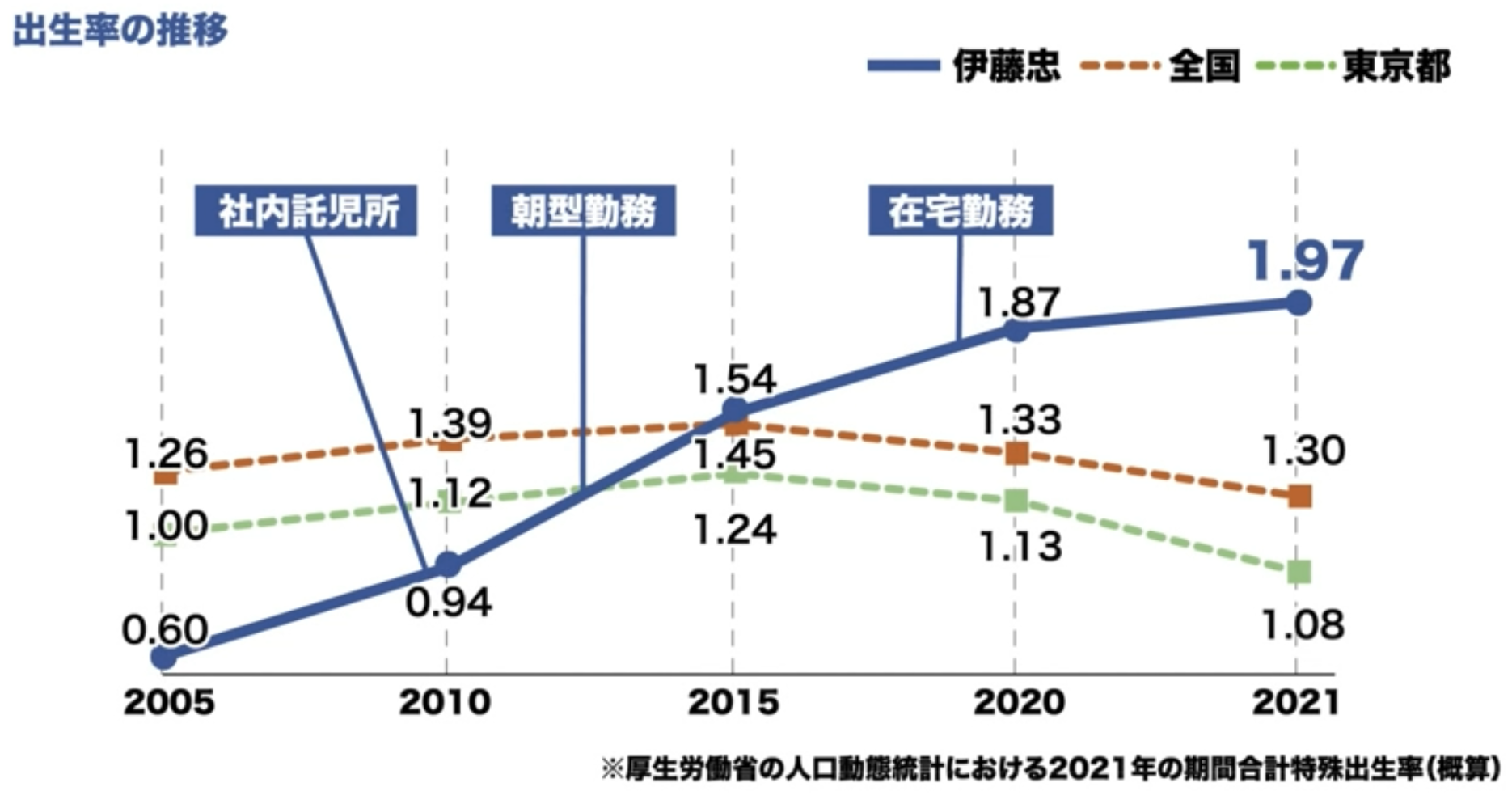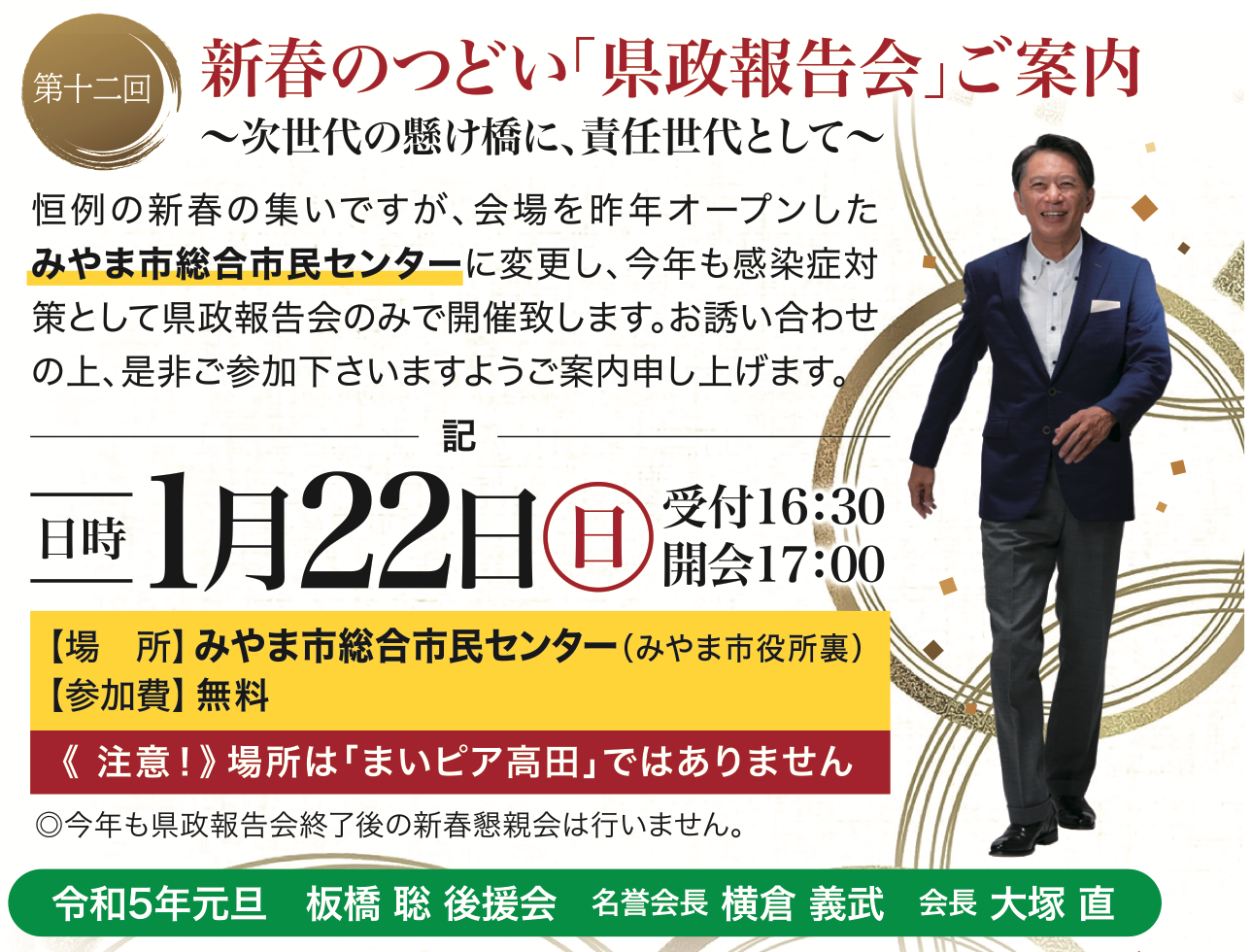昨日は足元の悪い中、私の新春の集い・県政報告会に多くの皆様のご出席を賜り大変有り難うございました。スタッフ一同どれ位の方にお集まり頂けるか心配しておりましたが、コロナ禍以前を超える600名近いご来場者数となり、スタッフ一同安堵すると同時に皆様のご期待の大きさに身が引き締まる思いです。

また藤丸代議士、松嶋市長、金子柳川市長、関大牟田市長、牛嶋みやま市議会議長・近藤柳川市議会議長はじめみやま市・柳川市・大牟田市の市議会議員の皆様、乗富幸雄JA福岡中央会会長はじめ各種団体・行政区の長の皆様から、ご多忙にもかかわらずご来賓として会に華を添えて頂き心より感謝申し上げます。
昨年オープンしたみやま市総合市民センター(MIYAMAX)を初めて会場として開催しましたが、不馴れなこともあり行き届かない点も多々あったと存じます。どうぞご容赦ください。

横倉義武後援会名誉会長、大塚直後援会長を筆頭とした、後援会メンバーは雨にもかかわらず屋外での駐車場や交通整理から、受付・誘導・後片付けまでお手伝い頂き本当に有り難うございました。皆さんのお陰で今年も素晴らしい県政報告会を行う事が出来ました。
関わって頂いた全ての皆様に心からの感謝を申し上げ、ワンヘルスの推進をはじめとする県南振興の為に今年も益々汗を流して参りたいと存じます。
引き続きの御指導御鞭撻宜しくお願い申し上げます。

(お越し頂けなかった方の為にも、県政報告のダイジェスト版を動画にしたいと思っていますが、しばらく時間が掛かりそうです。どうぞご理解ください🙇)