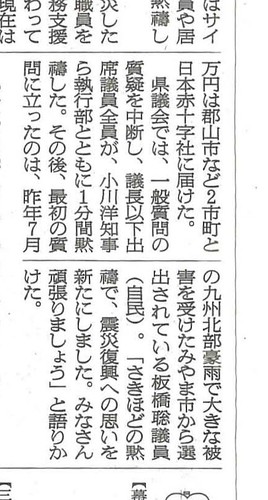◯板橋 聡委員 自民党県議団の板橋聡です。私ごとではありますが、私は子育て真っ最中で、本日は長男、長女の幼稚園の卒園式でございます。議員というのは因果な仕事で、私はここにこうしているわけでございますけれども、かくなる上は、県民のためにしっかりと仕事をいたしますので、執行部の皆さん、心して御答弁ください。
まずは、子育て支援についてお尋ねをします。
県が推進する子育て応援の店というものがあります。私の地元のある美容院も子育て応援の店に加盟しております。そこは、店舗の二階にキッズコーナーを設け、地元の子育てサークルと連携したりして保育士を配置し、充実した託児サービスを行っています。子育てで忙しい女性も安心して来店し、ゆっくりとサービスを受けて心身ともにリフレッシュすることができて、大変好評です。また、我が家も親子で何度もお世話になりました。
子育て応援の店はいろいろな形態があると聞いておりますが、このような特徴ある事例をもっと他社に参考にしてもらったり、努力、工夫をしている店へのインセンティブとして積極的に県民に対し広報したらいかがでしょうか。
◯原口剣生委員長 大田子育て支援課長。
◯大田子育て支援課長 子育て応援の店では、ミルクのお湯の提供や託児サービスなどの「やさしいサービス」や、キッズスペースの設置などの「便利な設備」、商品の割引などの「おトクなサービス」など、それぞれの店舗が取り組むことができるサービスの提供を通じて子育て家庭を応援していただいております。これらの取り組みは、子育て応援の店のホームページで紹介をしており、また、県の広報番組や子育て情報誌などを活用した広報にも取り組んでおります。今後、子育て応援の店の登録や利用のさらなる拡大を図るため、特徴的な取り組みなどについて、子育て応援の店のホームページを初め、県のさまざまな広報媒体を活用して紹介をしてまいりたいと考えております。
◯板橋 聡委員 県の施策を見ていますと、就労を軸とした女性の社会参加支援が充実しているように感じます。しかしながら、育児などのために家庭に入ることを選択した女性にもさまざまな形での社会参加があります。例えばPTAや自治会の会合に出席したり、公民館活動のお手伝いをしたり、勉強会や講演会に参加することも立派な社会参加です。その際、未就学児がいると、専業主婦であるがゆえに、逆に託児の問題が発生します。未就学児を子育て中の就労していない女性を支援する制度にはどのようなものがあるかをお教えください。
◯大田子育て支援課長 働いている、働いていないにかかわらず、子育て家庭を支援していくことは重要な課題であると認識をいたしております。子供を一時的に預かる事業といたしましては、保育所や子育て支援センターなどで子供を一時的に預かる一時預かり事業がありまして、今年度、四十八の市や町で実施されております。また、子育てのサポートを受けたい人とサポートをしたい人が会員となって相互に託児などを行うファミリー・サポート・センター事業につきましては、二十八の市や町でサービスが提供されているところでございます。
◯板橋 聡委員 一時預かりやファミリー・サポート・センターは、都市部では実施箇所も多く利用しやすいでしょうが、みやま市や八女市のような田舎には余りないですよね。子育てしやすい社会づくりのために、文化行事やセミナーなど、子育て家庭が参加する行事の場に託児コーナーを設置することが必要ではないかと思います。最初から全ての講習会、講演会でとは言いませんけれども、ここはまず県が率先して実施してみてはいかがでしょうか。県主催の講演会などでの託児コーナーの設置状況はどうなっていますか。また、今後の方策をお答えください。
◯大田子育て支援課長 今年度は、福岡県子育て応援宣言企業四千社突破!大会、あるいは青少年アンビシャス運動シンポジウムなど、県主催の九つのイベントなどにおいて託児コーナーが設置されております。今後とも、子育て家庭からたくさんの参加者が見込まれる県主催のイベントなどについては、担当部局に対して託児サービスの実施について働きかけてまいりたいと考えております。
◯板橋 聡委員 また、逆の視点で、民間を含め各種団体が子育て世代の母親向けに勉強会、イベントを行おうとしても、託児の問題が横たわって開催に大変苦労されているのです。例えばPTAの勉強会のような地域の会合における託児コーナーの設置促進について、県として何とか取り組みができないのでしょうか。
◯大田子育て支援課長 先ほどお答えいたしました福岡県子育て応援宣言企業四千社突破!大会など県のイベントでの託児の取り組み事例について、まずは市町村に対して積極的に紹介をしてまいりたいと考えております。
また、県では、高齢者がその豊かな経験や知識を生かして地域の子育て支援の現場で活躍していただく仕組みとして、今年度、ふくおか子育てマイスター制度を創設し、現在二百七十七名を認定しているところでございます。イベントなどにおける託児サービスの提供に当たっては、ぜひマイスターを活用していただくよう市町村を含め関係団体などに働きかけるとともに、マイスターが地域で活動しやすい仕組みづくりを進めてまいりたいと考えております。
◯板橋 聡委員 就労、未就労にかかわらず、全県的に子育てしやすい社会をつくることは地方の少子化問題の解決策にもなると思いますので、市町村への働きかけ、そしてマイスター制度、これは新しくできた制度ですけれども、この仕組みづくりも含め、これからしっかり子育て支援課には頑張っていただきたい。
高橋部長、部としてもしっかりサポートしていかないといけないと思いますので、決意をお聞かせください。
◯原口剣生委員長 高橋福祉労働部長。
◯高橋福祉労働部長 仕事と子育ての両立支援、あるいは地域において子育て支援を一体的にやっていくということは、委員が御指摘のように、少子高齢化が進展する我が国におきまして、市町村はもとより県といたしましても、そういうことを進めていくことが大変重要な課題であると認識しております。そういった点を十分に踏まえまして、これまでも子育て応援の店ですとか子育て応援宣言企業の拡大をやってまいりましたし、さまざまなイベントにおいて託児サービスの導入を働きかけてまいりました。それから、今年度から実施しておりますマイスター養成、ぜひいろいろな市町村だけではなく民間企業にも、このマイスターさんを活用していただく、そういうことをこれからも積極的に進めながら、子育てを支援できるような地域社会をつくってまいりたいと考えております。
◯板橋 聡委員 次に、ローソンとの包括協定についてお伺いいたします。
先日、ローソンと福岡県が包括協定を締結したとのプレスリリースがありました。私は、昨年六月議会及び決算特別委員会にて県と企業の包括協定についてさまざまな角度から問題点を指摘いたしました。にもかかわらずこれでは、二元代表制の一翼を担う議会を軽視しているように感じます。ローソンとの協定締結の経緯を御説明ください。
◯原口剣生委員長 重松社会活動推進課長。
◯重松社会活動推進課長 経緯でございます。昨年六月にローソンから包括協定の提案を受けましたが、議会でちょうど議論の最中でありましたことから凍結をしておりました。その後、十一月下旬に庁内での協議を始めまして、三月十三日に協定の調印に至ったところでございます。
◯板橋 聡委員 十一月下旬に庁内協議を開始されたということですから、私が六月議会及び決算特別委員会で問題点を指摘した後の協定締結と理解いたしますけれども、どう反映されたのでしょうか。
◯重松社会活動推進課長 今回の提携の協議に当たりましては、コンビニの特徴でもあります地域に密着した数多くの店舗があること、二十四時間の営業をされていること、若者の来店者が多いこと、こういった特徴を県として最大限に活用できるような提案を行いまして、県民サービスの向上あるいは本県の特性を生かしました地域の振興に資するような協議を進めてきたところでございます。
◯板橋 聡委員 イオンのときと余り変わらないことを言われているように聞こえるんです。ずばり、イオンのときのような、個別の電子マネーカード会員に加入させて、その売り上げに限る寄附などという、県の私企業に対する公平性、公正性を損なうような内容は入っているのでしょうか、いないのでしょうか。
◯重松社会活動推進課長 そのような寄附はございません。
◯板橋 聡委員 少なくともその点は改善が見られることがわかりました。
一方で、ローソンは三大コンビニチェーンの一つです。小川知事は、活力ある経済と雇用創出のためには中小企業の活性化が必要とおっしゃっています。県内企業の九割を占めるのは中小企業です。にもかかわらず、県が包括協定を締結するのはイオン、ローソンという地元商店街を圧迫している大企業ばかりです。中小企業に対しての配慮はないのでしょうか。
◯重松社会活動推進課長 コンビニチェーンの基本的な業態はフランチャイズでございます。県内のローソンの店舗の大半は、それぞれが地域に密着して活動しておられる小売店の経営者さんでございます。今回の協定はコンビニチェーンの運営会社でありますローソンと締結をするものですけれども、協定に基づく具体的な取り組みにつきましては、地域での社会貢献に資するよう、主に各店舗が取り組んでいかれるものであると認識しております。
◯板橋 聡委員 ちょっとピントがずれているような気がするんです。地域に根差した地場の企業に対してどういう配慮があるのかということをお答えください。
◯重松社会活動推進課長 県内の中小企業の皆さんが社会貢献活動に取り組みやすくなるように、企業向けに社会貢献の活動事例を紹介いたしましたメールマガジンを開始したいと思っております。また、業種、事業所の規模の大小にかかわらず、企業が社会貢献に取り組めるようにという思いから、現在、NPOと企業との協働のさまざまな取り組み事例を県内外から情報を収集しているところでございます。社会貢献活動に関心を持っていただいています企業さんに対しまして、こういった情報を積極的に提供してまいりたいと思っております。
◯板橋 聡委員 私はメールマガジンが余り好きではないんです。なぜかといえば、これは一方的な情報の垂れ流しのような気がするからです。それだけで中小企業にも配慮していますとはとても言えないのではないかと思います。もっと県として地域に出ていって中小企業と膝を突き合わせて情報交換を行うとか、そういった汗のかき方もあるのではないかと思いますけれども、いかがでしょう。
◯重松社会活動推進課長 中小企業家同友会におきまして新しく研修会を開催しようと思っております。この同友会の中に、平成二十三年、NPO交流・ソーシャルビジネス特別委員会という部会が設置されまして、ここで社会貢献等についてさまざまな勉強を行われるとお聞きいたしておりますので、そこに出かけていこうと思っておりますのが一つです。
それから、県内各地に出向きまして、社会貢献活動に対する地場企業の皆さん方の理解を深める取り組みを行い、企業による社会貢献活動の裾野を広げていきたいと思っております。まずは、福岡県商店街振興組合連合会の協力を得まして、県内各地で社会貢献活動の意義や方法について御説明申し上げようと思っております。
◯板橋 聡委員 中小企業に対する情報提供の働きかけ、取り組みを頑張っていこうという気持ちはよくわかりました。ただ、これは抜本的な中小企業に対する対応にはなかなかできないのかなと。これはぜひ継続して努力をして、中小企業の方に福岡県は頑張っているなと思っていただけるようにしていただきたいと思います。
ところで、視点を変えまして、福岡県はよく支店経済都市と呼ばれておりまして、大企業の支社、支店が多数存在しております。私自身も、議員になる前は某企業の九州支社で転勤族として勤務しておりました。そのときに漠然と感じたのは、大手企業に勤務していると、会社に対する帰属意識は物すごく強いのですけれども、居住地に対する帰属意識は薄い場合が多いということです。事実、私の周りの社員、特に転勤した方は、地元自治会や公民館の活動に興味が余りなかったんです。地域振興より会社の業績なのです。当たり前といえば当たり前ですけれども、それでは行政としては寂しい部分もございます。
地方自治の最小単位は地域の行政区です。その中において、昨今の住民の自治会離れは、議会などでも議題になっておりましたけれども、大きな行政課題だと認識しております。例えば、ローソン社員の自治会加入を促すことを協定に盛り込んだらいかがでしょう。
◯重松社会活動推進課長 この協定は、県とローソンが互いの業務について連携をするものでありますので、社員個人の取り組みにつきましては協定に盛り込むことは考えておりません。
◯板橋 聡委員 ただ、包括協定を結ぶときに、全庁的にローソンと取り組むときに何ができるかをヒアリングされたということも聞いております。直接的には自治会の加入とかに関してはそちらの部署の所轄ではないかもしれませんけれども、こういった提案はほかの部署から出てこなかったのでしょうか。
◯重松社会活動推進課長 庁内からそのような提案はございませんでした。
◯板橋 聡委員 今回の包括協定について、最初に重松課長が地域の振興に資するように協議してきたと言われております。もっと積極的に取り組むべきだと思うのですけれども、長谷川部長、いかがでしょう。
◯原口剣生委員長 長谷川新社会推進部長。
◯長谷川新社会推進部長 御指摘のとおり、町内会といった地域のコミュニティーにつきましては、防犯あるいは防災を初め、地域が抱える課題に対応していくためには大変重要な存在であると認識しているところでございます。私たちも、先ほどローソンの社員に対する御指摘がございましたけれども、こうした皆さんにも、こういう思いを持っていただいて、地域コミュニティーの活動に積極的に参加していただきたいという思いはございます。こうしたことから、ローソンに対しましても投げかけを行っていきたいと思います。
◯板橋 聡委員 ローソンに限らず、これから新たに包括協定を大企業と結ばれるかもしれませんけれども、そのときや、あるいは協定の更新の際に同様の投げかけを行っていただけませんでしょうか。
◯長谷川新社会推進部長 機会を捉えまして同様の投げかけを行いたいと思います。
◯板橋 聡委員 一歩踏み込んだ回答をいただきました。もちろん、企業に対して強制できるものではないということは私もわかっております。ただ、このような働きかけにより、大企業の社員の方も自治会活動を通じて地域に根づいた中小企業の方と同じ目線で地域活性化への意識を持ってもらえるとするならば、これは真に地域の活性化に資する包括協定になると思います。我々議会としても、ぜひ応援したいと思います。
逆に言うと、そんなことも理解せずに包括協定による地域の活性化とか言う企業はおためごかしです。だから、新規の包括協定なり既存協定の延長の際は、先ほどの答弁にもありましたとおり、ここをしっかり見きわめて、今後とも新社会推進部は真に地域の活性化に資する共助社会づくりを目指していただきたいと思います。
最後に、長谷川部長の決意をお聞かせください。
◯長谷川新社会推進部長 少子高齢化の中で、あるいは人口が減少していく将来像を考えますと、地域におきまして、行政だけではなくて、いろいろな主体が共助社会づくりを推進していただくということが極めて重要であると私は思っております。そういう意味では、最終的な目的である地域振興のために、地場の中小企業等にも十分に意を用いながら、幅広い企業や団体が行政やNPO、ボランティアなどと連携してまちづくりを進めていく、こういうことにしっかり取り組んでまいりたいと思います。今後とも、社会貢献活動に幅広い企業や団体の参画を求めまして、さまざまな取り組みを着実にやっていきたいと考えております。
◯板橋 聡委員 終わります。(拍手)