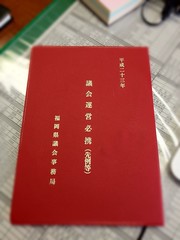本日、県議会議員になって初めての大規模な県政報告会を開催します。今まで会議室レベルのものはやっていたのですが、今回はまいピア高田の大ホールということで大変緊張しています。ブログの更新をサボっていたのもその準備や資料作りに忙殺されていたからでした。忙殺といっても現実逃避しそうになる自分との戦いでしたが。
今日は大きく3つの事について話をするつもりです。一つは「地方議会について知っておいて欲しい事」二つ目は「今、福岡県が考えていること」三つ目は「みやま市内における福岡県の主要事業」です。昨年4月30日に議員に就任して約9ヶ月、思いの丈をできる限りお伝えするつもりです。ご出席頂ける方、どうぞ宜しくお願いします。
ちなみに最近の私の机の上は下の写真のような訳の分からないカオス状態でした。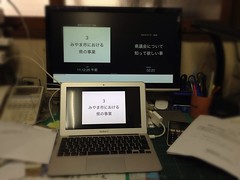
県政報告が終わったら先ずは机の横に溜まりに溜まった書類整備から始めたいと思います。
県政報告会の前に、本日は柳川市民会館にて「みやま・柳川 暴力団追放総決起大会」が開催されます。
福岡県警では全国で一番最初に暴力団排除条例を制定しているにも関わらず、つい先日も中間市で建設会社社長が暴力団から襲撃されるという事件が起こっています。近隣地区でも発砲や火焔瓶の投げ込みなど住民の安全安心を脅かす事件が頻発しており、近隣自治体一体となって暴力団追放の機運を盛り上げることが肝要です。